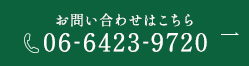角膜炎・角膜潰瘍の違い
 角膜炎とは、細菌・ウイルス感染、外傷などを原因として角膜で炎症が起こる病気です。目の充血、痛み、涙目、眩しさなどの症状を伴います。
角膜炎とは、細菌・ウイルス感染、外傷などを原因として角膜で炎症が起こる病気です。目の充血、痛み、涙目、眩しさなどの症状を伴います。
一方の角膜潰瘍は、角膜炎が進行するなどして、角膜組織が損傷している状態であり、角膜炎より事態は深刻です。強い痛みを伴い、視力低下を引きこすことがあります。
角膜炎は早期治療により十分な回復が見込めますが、放置していると角膜潰瘍へと進行する可能性があります。症状に気づいた時には、お早目に当院にご相談ください。
角膜炎の症状

- 充血
- 目の痛み
- 涙目
- 眩しさ
- ゴロゴロとした異物感
- 見えづらさ、視力低下(進行した場合)
角膜炎の原因
角膜炎の原因には、以下のようなものがあります。
細菌・ウイルス・真菌などの感染
細菌やウイルス、真菌(カビ)などの感染です。
不衛生なコンタクトレンズの装用、淡水・土壌との接触、流行性結膜炎(はやり目)からの移行などが主な原因となります。
特に免疫力が低下している時には、感染のリスクが高くなります。
外傷
外傷によって角膜上皮に傷がつくと、そこから病原体が感染し、角膜炎を起こすことがあります。
角膜が傷つく原因としては、異物(小さなゴミ)が侵入した状態での目を擦る行為、コンタクトレンズの物理的な刺激などが挙げられます。
アレルギー性結膜炎
花粉・ハウスダストなどを原因とするアレルギー性結膜炎の炎症が、角膜に及ぶことがあります。
ドライアイ
ドライアイになると、涙の量の不足、涙の層の不安定化などにより、角膜や結膜が傷つきやすい状態となります。ちょっとした刺激により角膜が傷つき、角膜炎が引き起こされることがあります。
免疫力の低下
免疫力が低下している時には、角膜に限らず、ウイルスや細菌に感染したり、発症したりするリスクが高くなります。ヘルペスウイルスを原因とする角膜ヘルペスがよく知られています。
角膜炎の検査
スリットランプ検査
細隙灯顕微鏡を使用して、角膜の混濁や炎症の程度を詳しく観察します。
フルオレセイン染色検査
フルオレセインという色素を点眼し、角膜の傷や炎症の範囲を確認します。
角膜培養検査
細菌・ウイルス・真菌・アカントアメーバなどの病原体が原因となっている場合、角膜の表面を擦過し、培養検査を行います。
PCR検査
ウイルス性角膜炎が疑われる場合、病原体の遺伝子を調べるために行います。
角膜感受性検査
ヘルペスウイルス感染が疑われる場合、角膜の知覚が低下していないかを確認します。
角膜炎の治療と治るまでの期間
感染性の角膜炎
細菌性角膜炎
抗生物質が配合された点眼薬による治療を行います。少なくとも、1~2週間の治療が必要です。
真菌性角膜炎
抗真菌性点眼薬、内服薬などによる治療を行います。治療期間は1~6ヶ月と、症例によって差があります。
角膜ヘルペス
抗ウイルス眼軟膏による治療を行います。治療期間は通常1~2週間ですが、再発を繰り返すことが少なくありません。医師の指示に従い、治療を継続しましょう。
アメーバ角膜炎
主に、消毒点眼薬、抗真菌点眼薬を使用します。治療期間は1~6ヵ月と、症例によって差があります。
アレルギー反応による角膜炎
病態・重症度に応じて、ステロイド点眼薬や内服薬を用いた治療を行います。
角膜潰瘍の症状

- 目の強い痛み
- 充血
- 涙があふれる
- 視力低下
- かすみ目
- ゴロゴロとした異物感
- 膿、粘性分泌物
角膜潰瘍の原因
角膜炎からの進展、外傷、コンタクトレンズトラブルなどが主な原因となります。
また、糖尿病、角膜ジストロフィーに合併して角膜潰瘍を発症することがあります。
角膜潰瘍の検査
スリットランプ検査
角膜の潰瘍の深さや広がり、周囲の炎症の状態を確認します。
フルオレセイン染色検査
潰瘍の範囲を詳しく調べるために行います。
角膜培養検査
細菌や真菌、アカントアメーバなどの感染が関与している可能性がある場合、病原体を特定するために行います。
PCR検査
角膜潰瘍が進行すると前房(角膜と虹彩の間の空間)に炎症を引き起こすことがあるため、前房の炎症や膿の有無を確認します。
角膜潰瘍の治療法
角膜潰瘍の原因に応じて、適切な治療法を選択します。
感染による角膜腫瘍
抗真菌薬の点眼・内服が主な治療となります。数ヶ月以上におよぶ長期の投与となるため、肝機能・腎機能障害が起こらないよう、定期的に検査を行います。
非感染性の角膜腫瘍
抗生物質、ステロイド薬の点眼治療が中心となります。ステロイドの内服、手術が必要になることもあります。
外傷による角膜腫瘍
原因菌を調べ、その結果に応じて適切な抗生物質が配合された点眼薬を処方します。症状が強い場合には、抗生物質の内服が必要になることもあります。
角膜炎・角膜潰瘍で失明する確率
 角膜炎については、早期に適切な治療が行われれば、完全な失明に至ることは非常に稀です。ただし、重症化した場合や治療が遅れる場合、角膜に大きなダメージを受け、視力が著しく低下するリスクはあります。
角膜炎については、早期に適切な治療が行われれば、完全な失明に至ることは非常に稀です。ただし、重症化した場合や治療が遅れる場合、角膜に大きなダメージを受け、視力が著しく低下するリスクはあります。
一方、角膜腫瘍(まれに角膜に発生する良性・悪性の腫瘍)も、中央部に発生した場合や悪性の場合、視力に大きな影響を与える可能性はあります。しかし、早期発見・治療によって失明のリスクは大幅に低減できます。
どちらの状態も適切な医療介入により失明のリスクは非常に低く抑えられますが、治療のタイミングや個々の症例によっては視力に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、異常を感じた際は早めの受診が重要です。