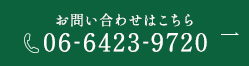網膜静脈閉塞症とは
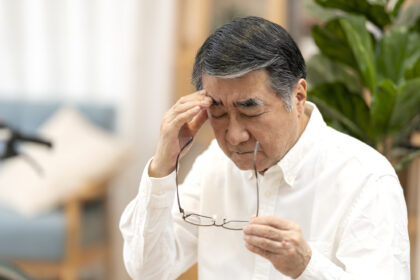 網膜静脈閉塞症とは、網膜の静脈が詰まる病気です。血流が滞ることで、黄斑浮腫や眼底出血を引き起こすことがあります。
網膜静脈閉塞症とは、網膜の静脈が詰まる病気です。血流が滞ることで、黄斑浮腫や眼底出血を引き起こすことがあります。
高血圧および動脈硬化が発症に大きく影響しており、このことから50代以降の方によく見られる眼疾患となっています。
網膜静脈閉塞症は、大きく以下の2つに分類されます。
網膜中心静脈閉塞症
眼球と脳をつなぐ「網膜中心静脈」が詰まるタイプです。
網膜全体に悪影響がおよび、眼底や黄斑での出血・浮腫などを招きます。出血は時間経過によって治まりますが、浮腫が残ることもあります。
比較的、若い世代で発症します。
網膜静脈分枝閉塞症
網膜の動脈と網膜が交差する部位が閉塞するタイプです。網膜静脈閉塞症のうち、大部分を占めます。
黄斑浮腫、眼底出血を引き起こします。出血が治まっても、浮腫が残る・視力が回復しないということがあります。
網膜静脈閉塞症の症状・見え方
網膜静脈分岐閉塞症
眼底出血の部位によっては、視野の一部または全体がぼやけて見えるといった症状を伴います。
また、浮腫が黄斑に及んでいる場合には、重度の視力障害を伴います。
網膜中心静脈閉塞症
黄斑に浮腫が生じることで、深刻な視力障害が引き起こされます。
硝子体出血を起こした場合には、飛蚊症、かすみ目などの症状を伴います。
新生血管が隅角に及び、失明に至るということもあります。
網膜静脈閉塞症の原因
 網膜静脈閉塞症の原因は、高血圧および高血圧に伴う動脈硬化にあります。
網膜静脈閉塞症の原因は、高血圧および高血圧に伴う動脈硬化にあります。
高血圧・動脈硬化によって網膜の静脈が圧迫されると、血栓が生じ、眼底出血・黄斑浮腫などを引き起こします。
その他、糖尿病の方、肥満の方なども、そうでない場合と比べると網膜静脈閉塞症の発症リスクが高くなると言われています。
網膜静脈閉塞症の検査
視力検査
網膜静脈閉塞症の症状の1つである、視力低下の有無を調べます。
眼圧検査
網膜静脈閉塞症は難治性の緑内障を合併することがあるため、眼圧を調べます。
眼底検査
目の奥にある眼底の状態を調べます。病変の範囲や血管の詰まりの程度が分かります。
OCT検査
網膜の断面図を観察する検査です。視力へと影響する黄斑部のむくみを評価します。
蛍光眼底造影検査
腕の静脈から造影剤を注射し、特殊なカメラで眼底を撮影することで血管の異常(血流の低下や漏れ)を詳しく調べます。黄斑浮腫や無血管領域の評価に用いられます。
網膜静脈閉塞症の治療
硝子体注射(抗VEGF療法)
黄斑浮腫、新生血管の活性化の原因となるVEGF(血管内皮増殖因子)の働きを阻害する「抗VEGF薬」を硝子体に注射する治療です。
即効性も高く、網膜静脈閉塞症に対してもっとも多く行われている治療です。
ステロイド局所注射
網膜静脈閉塞症によって眼内に炎症をきたし、黄斑浮腫が起こった場合に有効です。ステロイドの注射により、炎症を抑制します。
レーザー治療
網膜浮腫に対してレーザーを照射することで、網膜に溜まった血液成分を吸収させ、むくみの改善を図ります。
網膜静脈閉塞症の注射の効果と注意点
 注射治療は、黄斑浮腫による視力低下に対して有効で、第一選択として抗VEGF薬が用いられることが多いですが、抗VEGF薬が効きにくい場合や長期間の効果を求める場合にはステロイド注射が検討されます。いずれの治療も視力の改善や進行抑制に効果が期待できますが、必ずしも元の視力に戻るとは限らないため、継続的な経過観察と必要に応じた追加治療が重要です。
注射治療は、黄斑浮腫による視力低下に対して有効で、第一選択として抗VEGF薬が用いられることが多いですが、抗VEGF薬が効きにくい場合や長期間の効果を求める場合にはステロイド注射が検討されます。いずれの治療も視力の改善や進行抑制に効果が期待できますが、必ずしも元の視力に戻るとは限らないため、継続的な経過観察と必要に応じた追加治療が重要です。
抗VEGF薬の注射(ルセンティス、アイリーア、ベオビュなど)
効果
- 黄斑浮腫(網膜のむくみ)を抑え、視力の改善が期待できる。
- 早期に治療を開始すれば、視力低下を防ぎやすい。
- 1回の注射で効果が数週間〜数カ月持続するが、定期的な追加投与が必要な場合が多い。
注意点
- 効果には個人差がある。
- 繰り返しの注射が必要になることが多い(通常、最初は毎月、その後は状態に応じて間隔を調整)。
- 費用が高め(保険適用されるが、自己負担額がある)。
ステロイド薬の注射(マキュエイド、トリアムシノロンなど)
効果
- 抗VEGF薬と同様に、黄斑浮腫を軽減し、視力を改善する可能性がある。
- 効果が長期間(数カ月)持続することがある。
注意点
- 白内障や眼圧上昇(緑内障)のリスクがある。
- 特に眼圧上昇のリスクがあるため、定期的な眼科検査が必要。